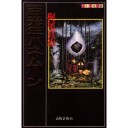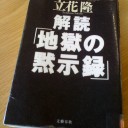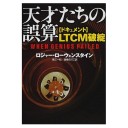ラルフ・E・ラップ著『福竜丸』
2011年12月21日 読書
原題が『The voyage of the Lucky Dragon』という古書を読んだ。広島、長崎に続いて被曝した日本人の物語。アメリカのラルフ・E・ラップ博士が関係者への取材を重ね、驚くべき構成力で福竜丸の航海の模様、被曝の瞬間、その後の日本社会の動揺を克明に描いている。公平な立ち位置を保ち、極めて客観的に書かれた価値ある資料だと感じた。当時はまだ戦争の記憶も生々しく、日本人にとって原子力、放射能は理解を超えた恐怖以外の何ものでもなかったことが読み取れる。そして、福竜丸の事件に日本中が心を痛めたことがわかる。
この本では触れてないが、その福竜丸の事件があった当時、すでに原子力発電所の計画が具体的に進められていたのだ。福竜丸の事件が起きて、原発計画は下火になるどころか、加速していくことになる。「原子力の平和利用」というスローガンの下に。福竜丸のことでも核の恐ろしさを見せつけられた日本が、原発大国へと歩みを進めたのはなぜか。だんだん、見えてくることがある。
この本では触れてないが、その福竜丸の事件があった当時、すでに原子力発電所の計画が具体的に進められていたのだ。福竜丸の事件が起きて、原発計画は下火になるどころか、加速していくことになる。「原子力の平和利用」というスローガンの下に。福竜丸のことでも核の恐ろしさを見せつけられた日本が、原発大国へと歩みを進めたのはなぜか。だんだん、見えてくることがある。
子どものころからタイムマシンの可能性について自分なりに考えていた。地球で起こったこと(映像)は光となって宇宙の彼方目指して飛びさって行く。だから光の速さよりも早く飛び、光を追い越して地球を望遠鏡でのぞいてみれば、過去の映像(光)を見ることができる。これってタイムマシンだよな、と思った。
梶尾真治の「百光年ハネムーン」が話題になっていたので読んでみたら、このアイデアまんまだったので、嬉しいやらなんやらワクワクしてハイになってしまった。さらに梶尾真治はこのアイデアを使ってとってもロマンチックな短編に仕立てていて、さすがだなー、またやられちゃったなー、と切ない気持ちになってうんうんうなづきながらそこらへんを徘徊。
アイデアはあるだけでは意味がない。それをどう使って、どういうものを創りだして、世に訴えるかが問題。この物語の中では過去をのぞけるタイムマシンを使ってとても魅力的な企画が仕立てられていた。その思考の積み重ね方と想像力は広告マンとして見習わなければならんなと思ったり。
梶尾真治の「百光年ハネムーン」が話題になっていたので読んでみたら、このアイデアまんまだったので、嬉しいやらなんやらワクワクしてハイになってしまった。さらに梶尾真治はこのアイデアを使ってとってもロマンチックな短編に仕立てていて、さすがだなー、またやられちゃったなー、と切ない気持ちになってうんうんうなづきながらそこらへんを徘徊。
アイデアはあるだけでは意味がない。それをどう使って、どういうものを創りだして、世に訴えるかが問題。この物語の中では過去をのぞけるタイムマシンを使ってとても魅力的な企画が仕立てられていた。その思考の積み重ね方と想像力は広告マンとして見習わなければならんなと思ったり。
雨ニモマケズ/風ニモマケズ……
2011年8月31日 読書大賢人ゲドはその力と魔法と引き替えに世界を救った。力と魔法を失った彼はなんの役にも立ちそうにもない一人の薄汚い老いぼれになった。彼を慕って遠い国からやってきた若者は、力のなくなった年老いた彼を人々が蔑むのを見て憤慨し、あなたは尊敬されるべきなのに、と文句を言うと、ゲドは「敬意などいらんよ。」と激しい剣幕で言い放った。私は同じような人間を知っている。宮澤賢治だ。
アースシー(Earthsea)を旅する
2011年8月27日 読書
アーシュラ・K・ル=グィンは大好きだったけど、「ゲド戦記」は後回しになっていた。ここ数日、この未来史にどっぷりハマる。ル=グィン女史が語るように、ファンタジーこそ真実、ということを実感しながら読んでいる。いちいち納得。ただ、子どもの頃に読んでおくべきだったな〜。そうすればこの本を読んだあとに長い長い探求の旅が楽しめたのに。でも今からでも遅くない♫
「地獄の黙示録」を解読する(少しね)
2011年8月24日 読書
この本は探していたわけではなく、図書館でなんとなく手に取ってしまった。映画「地獄の黙示録」は私が中学生のときに、連れられてではなく生まれて初めて観た映画。当時のクラスメイトと2人で観に行った。なんでこの映画を選んだのかはさっぱり覚えてない。観終わっても感激するでもなく、ぼ〜んやり。コッポラという監督が大好きなわけでもなく、この映画に対しては心理的に距離を置いていた、それでもずーっと心のどこかで気になっていた、というような感じ。だからシネヴィヴァン六本木で「ハート・オブ・ダークネス」を観たし、去年、特別完全版のLDを入手したりしていた。それを観ても、ふ〜ん、やっぱいいわ、ぐらいでぼんやり。
しかしこの立花隆の本を読んで、腑に落ちることばかり。この映画の下敷き、あるいは材料になっている西欧の聖杯伝説、コンラッドの「闇の奥」、映画の中にも登場するジェシー・ウェストン「儀式からロマンスへ」、フレイザー「金枝篇」、そしてドアーズの「THE END」……。どれも日本人の私からすると馴染みの薄いものだが、欧米の人たちの意識の奥底に共通して流れている思想のベースとなるものらしい。父殺し、継承者は聖なる王を殺して継承の資格を得る、自我同一性を確立する儀式、などなど。カーツとウィラードを父子としてみると、この映画に入っていきやすい。
ここで、あ〜、と気がつく。アーシュラ・K・ル=グィン「ゲド戦記」やオースン・スコット・カード「死者の代弁者」、奇異と思われる物語もこういう西欧人の意識・思想を理解することができれば、あーそうか、という感じ。「スターウォーズ」はとってもわかりやすい。アメリカ人は私みたいな日本人より、すごくすごく共感して「スターウォーズ」を観たに違いない。エディプス・コンプレックスを脱する、克服することはどういうことなのか、こんな大衆文化で共有できる社会はうらやましい。日本の家族はなかなか辛いもんがあったりする。
しかしこの立花隆の本を読んで、腑に落ちることばかり。この映画の下敷き、あるいは材料になっている西欧の聖杯伝説、コンラッドの「闇の奥」、映画の中にも登場するジェシー・ウェストン「儀式からロマンスへ」、フレイザー「金枝篇」、そしてドアーズの「THE END」……。どれも日本人の私からすると馴染みの薄いものだが、欧米の人たちの意識の奥底に共通して流れている思想のベースとなるものらしい。父殺し、継承者は聖なる王を殺して継承の資格を得る、自我同一性を確立する儀式、などなど。カーツとウィラードを父子としてみると、この映画に入っていきやすい。
ここで、あ〜、と気がつく。アーシュラ・K・ル=グィン「ゲド戦記」やオースン・スコット・カード「死者の代弁者」、奇異と思われる物語もこういう西欧人の意識・思想を理解することができれば、あーそうか、という感じ。「スターウォーズ」はとってもわかりやすい。アメリカ人は私みたいな日本人より、すごくすごく共感して「スターウォーズ」を観たに違いない。エディプス・コンプレックスを脱する、克服することはどういうことなのか、こんな大衆文化で共有できる社会はうらやましい。日本の家族はなかなか辛いもんがあったりする。
『天才たちの誤算 LTCM破綻』を読む
2011年8月10日 読書
これは再読。いろんな想いで読み返した。リーマン・ブラザーズ破綻の際にもそうだったが、マーク・トウェインの「歴史は繰り返すのではない、韻を踏むのみ」という言葉が思い出される。過去のデータを分析・解析したモデルにどれだけ重きを置くか。とくにネット時代になって多くの人が同じ情報を手にすることができるようになりつつある現在、それをどう生かすのか、に独創的なアイデアが必要なのではないか。もちろん、ブラック-ショールズ方程式は素晴らしく独創的でウォール街を席巻した。だが、ここでもそのツールをどう使うのか、扱うのかが鍵となった。
ブライアン・W・オールディスの小説。なぜか文庫を古本で買っていた。誰かのコラムで紹介されていて興味を持ったはずだが、思い出せない。正月休みに読んでみる。
小説は時間がかかると思ってここしばらく手を出していない。トーマス・マンの『ヨセフとその兄弟』もウイリアム・ギブソンの『あいどる』も、中途で何年間も放りっぱなし。だがこの『地球の長い午後』はさくさく読めて、2日間ほどで読破した。
読み始めてすぐに筒井康隆『メタモルフォセス群島』、宮崎駿『風の谷のナウシカ』などを連想。次世代の地球を描く試みはかなり前からあったんだ……。そういえば手塚治虫は『火の鳥』でそれやっているし。『地球の長い午後』は今から50年前の作品で、このテーマのオリジンではないだろうか。作者の想像力は驚異だ。
地球の自転が弱まり、自転と公転の周期が等しくなり、昼の部分は昼が続き、夜の部分は永遠に闇に包まれるようになった地球。そしてどんどん膨張していく太陽。地球の数億年後の姿としてありそうな設定。地球の昼の部分は植物に支配され、動物は駆逐され人類は姿形を変えてほそぼそと種を維持している。
読みながら立ち止まり、その未来の地球を頭の中でビジュアル化しようと努力してみる。小説を読みながら、小説に喚起され頭の中に広がるイメージはSF映画よりもリアルだ、というのが私の持論だが、この作品に関してはなかなか難しい。なんかしっくりイメージできないまま、先を急いで読んでしまった。
なるほどディスカバリーチャンネルの『フューチャー・イズ・ワイルド』はとてもよくできた成功例だ。あの映像はとても説得力があり、好感が持てた。ただ、あの映像もあくまでも美しく整理されているが、実際の世界はもっとめちゃくちゃでこんがらがっていて、カオスなはず。もっと汚いはず。汚いものをイメージするのは難しい。
物語の締めくくりはかなりあっけない。想像し得た結末だった。でもがっかり感はなく、そうだよな、という共感がある。21世紀に生きているから共感できたのかも、とさえ思える。SFは予言の書であり、おさらいする復習の書でもある。10年後20年後、数百年後、数億年後、未来を想像することはとても大事なことだと思う。
小説は時間がかかると思ってここしばらく手を出していない。トーマス・マンの『ヨセフとその兄弟』もウイリアム・ギブソンの『あいどる』も、中途で何年間も放りっぱなし。だがこの『地球の長い午後』はさくさく読めて、2日間ほどで読破した。
読み始めてすぐに筒井康隆『メタモルフォセス群島』、宮崎駿『風の谷のナウシカ』などを連想。次世代の地球を描く試みはかなり前からあったんだ……。そういえば手塚治虫は『火の鳥』でそれやっているし。『地球の長い午後』は今から50年前の作品で、このテーマのオリジンではないだろうか。作者の想像力は驚異だ。
地球の自転が弱まり、自転と公転の周期が等しくなり、昼の部分は昼が続き、夜の部分は永遠に闇に包まれるようになった地球。そしてどんどん膨張していく太陽。地球の数億年後の姿としてありそうな設定。地球の昼の部分は植物に支配され、動物は駆逐され人類は姿形を変えてほそぼそと種を維持している。
読みながら立ち止まり、その未来の地球を頭の中でビジュアル化しようと努力してみる。小説を読みながら、小説に喚起され頭の中に広がるイメージはSF映画よりもリアルだ、というのが私の持論だが、この作品に関してはなかなか難しい。なんかしっくりイメージできないまま、先を急いで読んでしまった。
なるほどディスカバリーチャンネルの『フューチャー・イズ・ワイルド』はとてもよくできた成功例だ。あの映像はとても説得力があり、好感が持てた。ただ、あの映像もあくまでも美しく整理されているが、実際の世界はもっとめちゃくちゃでこんがらがっていて、カオスなはず。もっと汚いはず。汚いものをイメージするのは難しい。
物語の締めくくりはかなりあっけない。想像し得た結末だった。でもがっかり感はなく、そうだよな、という共感がある。21世紀に生きているから共感できたのかも、とさえ思える。SFは予言の書であり、おさらいする復習の書でもある。10年後20年後、数百年後、数億年後、未来を想像することはとても大事なことだと思う。
ちいさいおうちと水辺
2010年12月24日 読書
姪っこの3歳の誕生日プレゼントは「ちいさいおうち」。私が絵本というと真っ先に思い出す大好きな作品。いろんな人にプレゼントしてきた。なぜか自分の手元にはないけど。
この絵本の中で私がいちばん気に入っているのは、最初の土地にあった池。ちいさいおうちのすぐ横、庭にきれいな池があって、そこから小川が流れ出ている。その環境、風景に子どもの私は魅了された。
夏はその池で子どもたちが水遊びをし、冬は凍った池でスケートを楽しんでいた。たしか魚釣りもしていたような気がする。たぶんこの絵本の影響だと思うのだが、まだ両親が家を建てる前、家を建てるなら庭に池を作ろうね、と小学生の私は両親におねだりしていたと記憶している。
絵本のなかでは、都会に取り残され、見捨てられたかたちになったちいさいおうちが、やっと家族と再会して静かな田舎に引っ越し・移設される。新しい土地でちいさいおうちと家族が落ち着いて幸せな暮らしを始めるので、めでたしめでたしなわけだが、子どもの私はその新しい土地には池と小川がないことが非常に残念だった。嬉しさも半分かな~、ぐらいに。水辺があるのとないのでは、豊かさの感じ方がぜんぜん違うのだ。贅沢すぎ(笑)。
さて、姪っこはこの絵本を読んで、どんなことを感じてくれるだろうか。
この絵本の中で私がいちばん気に入っているのは、最初の土地にあった池。ちいさいおうちのすぐ横、庭にきれいな池があって、そこから小川が流れ出ている。その環境、風景に子どもの私は魅了された。
夏はその池で子どもたちが水遊びをし、冬は凍った池でスケートを楽しんでいた。たしか魚釣りもしていたような気がする。たぶんこの絵本の影響だと思うのだが、まだ両親が家を建てる前、家を建てるなら庭に池を作ろうね、と小学生の私は両親におねだりしていたと記憶している。
絵本のなかでは、都会に取り残され、見捨てられたかたちになったちいさいおうちが、やっと家族と再会して静かな田舎に引っ越し・移設される。新しい土地でちいさいおうちと家族が落ち着いて幸せな暮らしを始めるので、めでたしめでたしなわけだが、子どもの私はその新しい土地には池と小川がないことが非常に残念だった。嬉しさも半分かな~、ぐらいに。水辺があるのとないのでは、豊かさの感じ方がぜんぜん違うのだ。贅沢すぎ(笑)。
さて、姪っこはこの絵本を読んで、どんなことを感じてくれるだろうか。