「地獄の黙示録」を解読する(少しね)
2011年8月24日 読書
この本は探していたわけではなく、図書館でなんとなく手に取ってしまった。映画「地獄の黙示録」は私が中学生のときに、連れられてではなく生まれて初めて観た映画。当時のクラスメイトと2人で観に行った。なんでこの映画を選んだのかはさっぱり覚えてない。観終わっても感激するでもなく、ぼ〜んやり。コッポラという監督が大好きなわけでもなく、この映画に対しては心理的に距離を置いていた、それでもずーっと心のどこかで気になっていた、というような感じ。だからシネヴィヴァン六本木で「ハート・オブ・ダークネス」を観たし、去年、特別完全版のLDを入手したりしていた。それを観ても、ふ〜ん、やっぱいいわ、ぐらいでぼんやり。
しかしこの立花隆の本を読んで、腑に落ちることばかり。この映画の下敷き、あるいは材料になっている西欧の聖杯伝説、コンラッドの「闇の奥」、映画の中にも登場するジェシー・ウェストン「儀式からロマンスへ」、フレイザー「金枝篇」、そしてドアーズの「THE END」……。どれも日本人の私からすると馴染みの薄いものだが、欧米の人たちの意識の奥底に共通して流れている思想のベースとなるものらしい。父殺し、継承者は聖なる王を殺して継承の資格を得る、自我同一性を確立する儀式、などなど。カーツとウィラードを父子としてみると、この映画に入っていきやすい。
ここで、あ〜、と気がつく。アーシュラ・K・ル=グィン「ゲド戦記」やオースン・スコット・カード「死者の代弁者」、奇異と思われる物語もこういう西欧人の意識・思想を理解することができれば、あーそうか、という感じ。「スターウォーズ」はとってもわかりやすい。アメリカ人は私みたいな日本人より、すごくすごく共感して「スターウォーズ」を観たに違いない。エディプス・コンプレックスを脱する、克服することはどういうことなのか、こんな大衆文化で共有できる社会はうらやましい。日本の家族はなかなか辛いもんがあったりする。
しかしこの立花隆の本を読んで、腑に落ちることばかり。この映画の下敷き、あるいは材料になっている西欧の聖杯伝説、コンラッドの「闇の奥」、映画の中にも登場するジェシー・ウェストン「儀式からロマンスへ」、フレイザー「金枝篇」、そしてドアーズの「THE END」……。どれも日本人の私からすると馴染みの薄いものだが、欧米の人たちの意識の奥底に共通して流れている思想のベースとなるものらしい。父殺し、継承者は聖なる王を殺して継承の資格を得る、自我同一性を確立する儀式、などなど。カーツとウィラードを父子としてみると、この映画に入っていきやすい。
ここで、あ〜、と気がつく。アーシュラ・K・ル=グィン「ゲド戦記」やオースン・スコット・カード「死者の代弁者」、奇異と思われる物語もこういう西欧人の意識・思想を理解することができれば、あーそうか、という感じ。「スターウォーズ」はとってもわかりやすい。アメリカ人は私みたいな日本人より、すごくすごく共感して「スターウォーズ」を観たに違いない。エディプス・コンプレックスを脱する、克服することはどういうことなのか、こんな大衆文化で共有できる社会はうらやましい。日本の家族はなかなか辛いもんがあったりする。
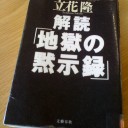

コメント